こんにちは!海外帰りの寿司屋の娘Satomiです!
このブログでは、すしを通じて日本文化を楽しく学び、日本の良さを活かしたグローバルなヒントをお届けしています!
今回は、「包丁」に注目!
日本料理といえば「包丁さばき」。
実は、日本には驚くほどたくさんの種類の包丁があるんです。
それはなぜか?――「切る」ことが命だから!?
たとえば中国料理では、大きな「菜刀(さいとう)」1本で何でも切っちゃうのが一般的。
対して日本料理は、魚、肉、野菜、それぞれに合わせた“専用包丁”を使い分けます。
ちなみに「包丁」という言葉、実は古代中国の料理人*「庖丁(ほうてい)」の名前から来ているって知ってました?
もともとは人名だったんですね。それが日本で「料理用の刃物」を指す言葉になったという面白エピソードも。
*諸説あり。
・人物名ではなく役職の名前である
・庖という役職の丁という名前の人だった
・庖という名前の丁という役だった など
🔪主な包丁ラインナップ(あなたはいくつ使ったことある?)
① 三徳包丁(さんとくぼうちょう)
家庭のヒーロー!肉・魚・野菜、全部いける万能選手。
→「三徳=三つの得意分野」って意味です。
② 出刃包丁(でばぼうちょう)
厚い刃で魚を豪快にさばく!鶏にも対応できるパワータイプ。
③ 菜切り包丁(なきりぼうちょう)
その名の通り「野菜専用」。まっすぐな刃が特徴で、ザクザク刻めます。
④ 刺身包丁(さしみぼうちょう)
引くだけでスッと切れる、繊細な職人技が光る一本。
魚の身を美しく仕上げるために、長〜い刃がポイント。
⑤ ふぐ引き包丁(ふぐびき)
薄くて超鋭い!ふぐを美しく、しかも安全にスライスするための特別仕様。
⑥ 鱧切り包丁(はもぎりぼうちょう)
鱧の小骨を断ち切るための大きめの包丁。ガツンと力強い一刀!
⑦ 蕎麦切り包丁(そばきりぼうちょう)
蕎麦職人の魂。下まで刃がついていて、まっすぐ均等に切れるデザイン。
🌍文化の違いに学ぶ
西洋のナイフも「肉専用」など複数ありますが、
日本ほど「食材ごとに専用」が進化してる国はめずらしいかも。
それだけ、食材を尊重し、丁寧に扱う文化が根付いてるんですね。
🎤あなたは何本使ったことある?
普段の料理では三徳包丁が定番かもですが、
出刃や刺身包丁を使ったことがある人もいるかもしれませんね!
コメントやSNSでぜひ教えてください✨
🎥 YouTubeでも公開中!
このチャンネルでは、日本の食文化やすしにまつわる面白い話を発信しています。
チャンネル登録といいねボタンを押して、次回の動画もお見逃しなく!
すしを通して、日本文化を一緒に学びましょう🍣🐆
参照:『それ日本と逆?!文化のちがい 習慣のちがい』 監修 国立民俗学博物館長 須藤健一
お知らせ✨
寿司職人の皆さんへ!
現在、アドバイザリーサービスとして、寿司職人向けのアンケートを実施中です。ご回答いただいた方には、なんと半額でサービスを提供いたします!
詳細は下のリンクからチェックしてみてくださいね。
日本の伝統を守りつつ、新しい時代に適応するお手伝いをしています。水のように柔軟で確かなサポートを提供しますので、ぜひご相談ください!
このブログが参考になったと思った方は「いいね!」やシェアをお願いします!✨
それでは、また次回お会いしましょう!
オススメ講座のご紹介
「すし付き講座」では、寿司屋では味わえない特別な楽しみ方が体験できます!
もっと寿司について学びたい!と思った方は、ぜひ「すし付き講座」にご参加ください!🍣✨
この講座では、江戸前寿司の文化や歴史を学びながら、プロが握る本格的なお寿司も楽しめます。
寿司を食べるだけでは味わえない、日本文化に触れる特別な体験を提供します。
寿司屋で食べるのとは一味違う、深い味わいと学びの時間をぜひ体験してください!
すしを通して日本文化を学び、グローバルな視点を持つスキルを身につけて、世界で活躍できる自分を目指しましょう!🌍💖
江戸前寿司の基本から、その魅力をしっかり学べる講座です。寿司の歴史や文化を知り、プロが握る本格寿司を楽しみながら、気軽に学べます。
🍣✨一押し講座🍣✨
- 【玉元芸人コース】
握り寿司と巻き寿司でライバルに差をつけよう!寿司文化を深く知りながら、食事の場で活躍できる知識とマナーを身につけることができます。 - 【プリン酢コース】
デートや食事会でカッコよくエスコートできるスキルを学べます。寿司の知識を会話に自然に取り入れ、相手に素敵な印象を与えましょう! - 【ガリウッドコース】
クイズ形式で楽しく寿司ネタの背景を学び、日本文化の美学を理解する講座です。
どの講座も、すしを通して日本文化を楽しく学び、グローバルな視点を身につける内容です。ぜひご参加ください!

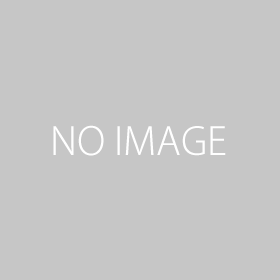
この記事へのコメントはありません。